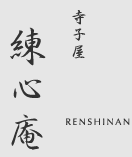2015/04/17 練心庵落語会 四月席

記:納谷久美子
練心庵、恒例の落語会。
今回は「くしゃみ講釈」でした。
怖い顔で、難しいことばかり言う講釈師が、真っ暗な夜道を歩いていると、なんと・・・!!何をしたかは、この落語を聞いたことがない人のために、ナイショにしておきますが、真っ暗で何も見えなかったので、ある男に、ひどいことをしてしまいました。
その男は、講釈師に仕返しをしようと、いろいろな方法を考えます。そして「胡椒でくしゃみをさせて、講釈ができんようにしたらええ。」というアドバイスを受けます。よっしゃ!やっと題名の「くしゃみ」が出てきたぞ!
前半は、その胡椒を買いに行く話、後半は、実際に使ってみる話です。この男は、なぜか「どこそこの八百屋」「胡椒」「2銭」が、なかなか覚えられません。
「どこで買うんやったかいな。…あー、せやせや、どこそこの八百屋やったな。わかった。んで、何を買うんやったかいな。…あー、せやせや、胡椒やったな。んで、なんぼ買うんやったかいな。…あー、せやせや、2銭やったな。んで、どこで買うんやったかいな。」そんなに物覚えが悪いならメモして行きんかいな…。でも、「のぞきからくり」の口上は丸ごとすらすら言えるので、その中に出てくるせりふを使って、だじゃれで暗記します。でも、どの部分でダジャレにしたのかを忘れてしまいます。ほんまに、どんだけよう忘れんねん。それで、「こしょう」というせりふがでてくるところまで全部言って、えらい時間がかかります。
さて、この「のぞきからくり」とは何ぞや?落語のあと、陸奥さんによる解説がありました。お金を払って、凸レンズ(虫メガネのレンズ。ものが大きく見える)をのぞくと、向こうに絵が見えます。紙芝居のように絵が変わっていきます。お金を払って見ている人が「わー!すごいなあ!」など言うので、「何や何や?!」「見たいわあ~!」と、どんどん人が集まってくるそうです。
この落語のはじめのほうに「東京が江戸やった時代?そんなん、まだ生まれてへんかったから知らん!」というせりふが出てきます。ということは、明治中期以降が舞台ですね。落語の舞台は、江戸時代ばかりではないのです。